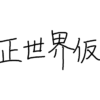恒常性
constancy phenomenon
今回は恒常性についてです。この記事では、特に知覚の恒常性についてを扱います。
知覚の恒常性
同一の刺激対象を異なる条件において見る場合、網膜像は変化しているにもかかわらず、その対象の見え方はこうした生理的変化とは無関係に一定不変のものとして感じられることを言います。この恒常性は、大きさ、形、明るさ、などで起こります。
大きさの恒常性
対象が近づいてくるにつれ、網膜像は大きくなりますが、その対象の見かけの大きさは変わりません。この恒常性を利用した例として、『エイムズの部屋』や『月の錯視』が挙げられます。それぞれについて個別記事を作成しています。(月の錯視については未作成ですので、外部の記事を参考にされてください。)恒常性の理由として、ここでは2つの考え方をご紹介します。
・大きさ・距離不変仮説
大きさが一定ならば、見かけ上の大きさは距離に比例する。また、視対象の大きさの近くが、網膜像に依存して決まるのではなく、距離も勘定に入れて判断しているから。という考え方です。
・対象の熟知度
熟知した対象ならば、その客観的大きさをすでに知っており、その網膜像の大小により対象までの距離が自動的に見積もられるから。という考え方です。
以上2点から、大きさの恒常性が働くのには、純粋に網膜像だけでなく、距離やもともとの大きさなど、見る人の考えも組み込まれていることがわかりますね。実際に目の錯覚の展示会などで恒常性が使われている作品なども多くあるため、ぜひ足を運んでみてください。
今回はここまでです。お疲れさまでした。